☑️【2分で読める要約版】
片麻痺の歩行訓練は、健側主導が新常識に
従来の片麻痺の歩行訓練は、患側を自力で動かすことに重きを置いてきましたが、筋緊張の亢進や動作の誤学習を招くことも少なくありませんでした。
近年注目されているのが、「健側下肢の力で患側下肢を振り出す」という歩行練習法。これは健側の股関節伸展と足関節底屈によって身体全体を前方へ移動させる仕組みです。
このアプローチにより、
- 重度の片麻痺患者が180mの歩行を達成
- 痙性の抑制(クローヌスの消失や関節拘縮の改善)
- 脊髄内の中枢パターン発生器(CPG)の活用による運動誘導
といった成果が報告されています。結論として、”「患側を頑張らせる」のではなく「健側で患側を動かす」”という視点が、片麻痺リハビリの新しい常識になりつつあります。
現場でも積極的な導入と治療成績の蓄積が求められています。
片麻痺患者の歩行練習、そのやり方…間違っていませんか?
従来の片麻痺患者に対する歩行練習は、実は“間違っていた”のかもしれません。
現在注目されているのは、”「健側下肢を使って患側下肢を振り出す」”という歩行練習の方法です。このアプローチによって、歩行の再獲得が劇的に促進されるケースが増えています。
なぜ従来の歩行練習はうまくいかなかったのか?
従来の歩行練習は、患側を自力で動かすことを前提とし、平行棒内で健側手→患側下肢→健側下肢の順に動作を進める「3動作揃え型歩行」が主流でした。しかし、麻痺側は随意性が低く、筋緊張も亢進しやすいため、こうした動作は過剰努力や異常運動パターンの誘発につながりやすいとされています。
一方、新しい歩行練習では健側の運動を活かして患側下肢を前方へ運ぶという逆転の発想が採用されています。健側の股関節伸展と足関節底屈の連動で身体ごと前進するこの方法は、患側の筋緊張を高めることなく、より自然な運動学習を促すことができます。
新たな練習法のキモは「健側主導」にある
垂直手すりと補高靴で始めるステップ練習
新たな練習法では、垂直手すりを利用して健側から一歩前に出し、股関節伸展と足関節底屈の力で患側を振り出します。患側のtoe clearance(足が床に引っ掛からない状態)を確保するために、健側に3cmの補高を施した靴を履かせるなどの工夫も有効です。
驚異の回復例:重症片麻痺者が180mを歩いた!
報告によれば、Brunnstrom Recovery StageがⅢ、深部感覚が中等度鈍麻、バランススケール(FBS)28点という重度片麻痺の症例が、この新しい練習法によって6分間歩行180mを達成しています。通常、監視歩行や杖歩行が可能になるにはFBS 40点以上が目安とされているため、これは驚異的な成果です。
痙性にも効果あり?セラピストが実感する変化
さらに、健側主導のステップ練習により痙性の抑制効果も報告されています。クローヌス(反復性筋収縮)の消失、踵接地の改善、膝屈曲拘縮の軽減といった成果が見られ、患者自身も運動の“楽さ”を実感することが多いようです。
神経生理学が後押しする新しい歩行のかたち
このアプローチには神経学的な裏付けもあります。脊髄内に存在する”中枢パターン発生器(CPG)”が、健側の筋活動を通じて患側の筋活動を間接的に誘導する働きがあるとされ、随意性がなくても歩行パターンは形成可能と考えられているのです。
歩行練習は「患側を動かす」から「健側で動かす」時代へ
片麻痺の歩行訓練における主役は、実は「健側」だったのです。
従来の「患側を頑張らせる」アプローチから、「健側で患側をコントロールする」方法へと発想を転換することで、より短期間で実用的な歩行を再獲得することが可能になります。
もちろん、この新しい方法は万能ではありませんが、動作学習の誤りを減らし、患者のポテンシャルを最大限に引き出す可能性を秘めています。現場の理学療法士としては、この新たな視点をもって歩行練習の方法を見直す時期に来ているのかもしれません。
まとめ
- 従来の「患側主導」の歩行練習には限界がある
- 「健側主導」による振り出しで、短期間に効果が出る症例も
- 痙性の抑制や中枢パターン発生器との整合性も確認されている
- リハビリの成果を最大化するには、新たな視点の導入が必要
理学療法士として、いまこそ「当たり前」を問い直すときかもしれません。
参考文献
山﨑裕司(2024).片麻痺患者の歩行練習は間違っていた!―健側下肢による患側下肢の振出し―.高知リハビリテーション専門職大学 特別寄稿.
JSTAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
※詳細な内容に関心のある方は、原著をご参照ください。
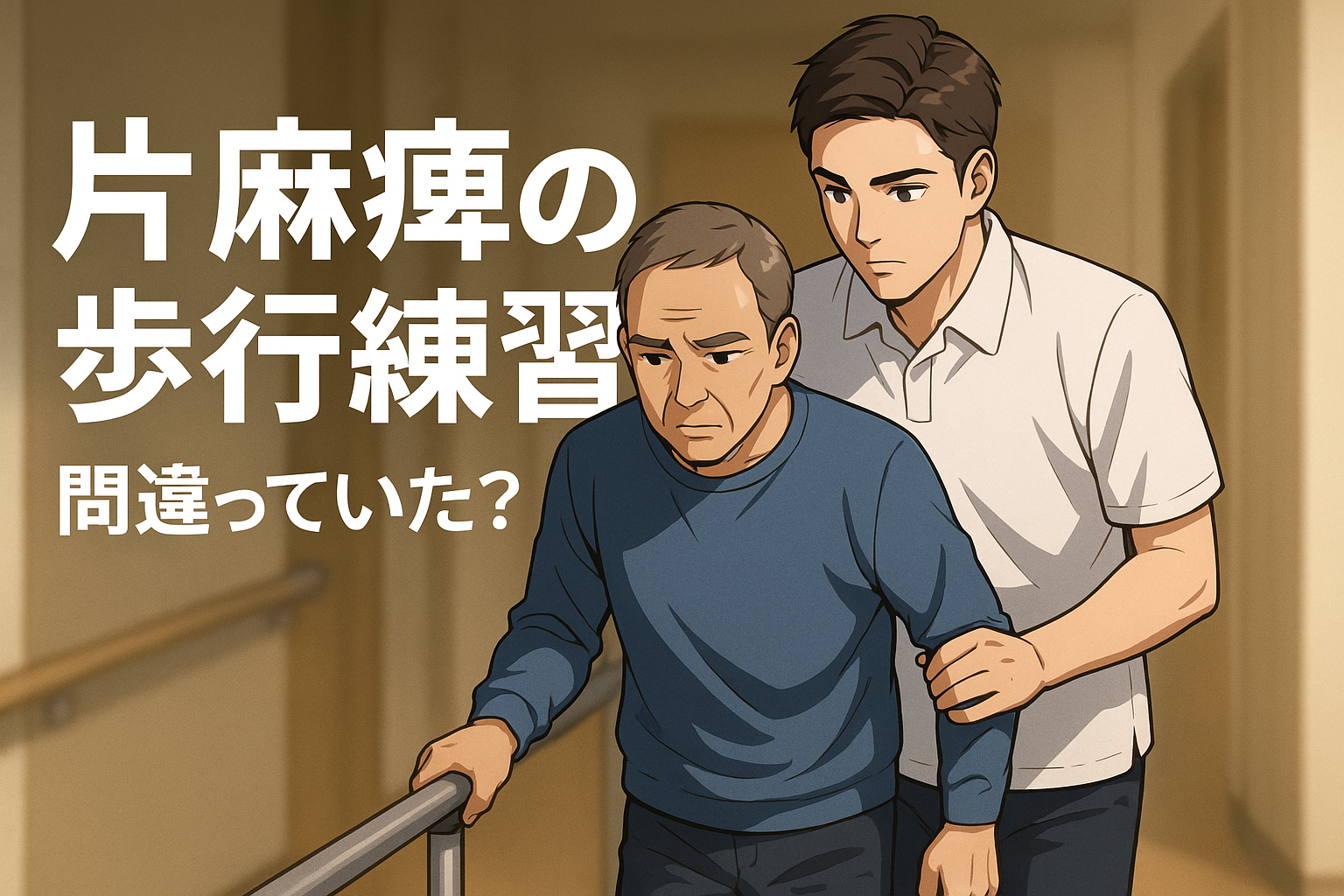


コメント